ナマサプリBLOG

コエンザイムQ10を摂りましょう!
みなさん、こんにちは。 今日はご当地キャラクターの日だそう。その理由は、5(ご)10(とう)+1(ち)という語呂から来ているようで😊1日ほんわか過ごそうと思います。 それでは、本日もコエンザイムQ10のお話。 先日のブログでは、コエンザイムQ10がどんな成分、役割で、そして、コエンザイムQ10の体内生成が年齢によって減少していき、1日に必要なコエンザイムを摂取しようとすると、ものすごい量の食品を摂取しなければいけない、というお話をさせて頂きました。 本日は、そのものすごい量の食品を摂取した方がいい、コエンザイムQ10のメリットをお伝えしようと思います。 [コエンザイムQ10のメリット] コエンザイムQ10は元気に生きていく上で、また、老化防止や美肌維持などの為に、とても大切なで、必要不可欠な成分であるとお伝えしました。 そして、コエンザイムQ10には他にもこんなにも多くのメリットがあるんです! ■元気ハツラツ! ■お肌の老化、からだの老化を予防! ■からだの疲れ改善! ■朝のすっきりとした目覚めを徹底サポート! ■ダイエットサポート! ■集中力のアップ! ■いびきの改善! ■生活習慣病の予防! ■関節痛の改善! ■心機能をサポート! ■抗酸化パワーの無くなったビタミンEの再生をサポート! いかがでしょうか。コエンザイムQ10のメリットは山ほどあります。 お肌やダイエットもそうですが、何よりもお伝えしたいのは、 ”毎日を元気に、そして、朝から気持ち良いスタートを切るためにもとっても大切な成分” ということです。 からだの中でしっかりとエネルギーを作り出し、日々の疲れをしっかり取り、そして、翌朝のパッとした気持ち良い目覚め。コエンザイムQ10をしっかり補給すると、本当に気持ちよく目覚めることができるので、朝の目覚めにお悩みの方は是非コエンザイムQ10の摂取をおすすめします! [コエンザイムQ10が足りてない?] 以下に心当たりのある方は、コエンザイムQ10が足りていない可能性がありますので、是非一度チェックしてみてくださいね。 疲れやすい 疲れが取れない からだがだるい、重い感じがする...
コエンザイムQ10を摂りましょう!
みなさん、こんにちは。 今日はご当地キャラクターの日だそう。その理由は、5(ご)10(とう)+1(ち)という語呂から来ているようで😊1日ほんわか過ごそうと思います。 それでは、本日もコエンザイムQ10のお話。 先日のブログでは、コエンザイムQ10がどんな成分、役割で、そして、コエンザイムQ10の体内生成が年齢によって減少していき、1日に必要なコエンザイムを摂取しようとすると、ものすごい量の食品を摂取しなければいけない、というお話をさせて頂きました。 本日は、そのものすごい量の食品を摂取した方がいい、コエンザイムQ10のメリットをお伝えしようと思います。 [コエンザイムQ10のメリット] コエンザイムQ10は元気に生きていく上で、また、老化防止や美肌維持などの為に、とても大切なで、必要不可欠な成分であるとお伝えしました。 そして、コエンザイムQ10には他にもこんなにも多くのメリットがあるんです! ■元気ハツラツ! ■お肌の老化、からだの老化を予防! ■からだの疲れ改善! ■朝のすっきりとした目覚めを徹底サポート! ■ダイエットサポート! ■集中力のアップ! ■いびきの改善! ■生活習慣病の予防! ■関節痛の改善! ■心機能をサポート! ■抗酸化パワーの無くなったビタミンEの再生をサポート! いかがでしょうか。コエンザイムQ10のメリットは山ほどあります。 お肌やダイエットもそうですが、何よりもお伝えしたいのは、 ”毎日を元気に、そして、朝から気持ち良いスタートを切るためにもとっても大切な成分” ということです。 からだの中でしっかりとエネルギーを作り出し、日々の疲れをしっかり取り、そして、翌朝のパッとした気持ち良い目覚め。コエンザイムQ10をしっかり補給すると、本当に気持ちよく目覚めることができるので、朝の目覚めにお悩みの方は是非コエンザイムQ10の摂取をおすすめします! [コエンザイムQ10が足りてない?] 以下に心当たりのある方は、コエンザイムQ10が足りていない可能性がありますので、是非一度チェックしてみてくださいね。 疲れやすい 疲れが取れない からだがだるい、重い感じがする...

コエンザイムQ10ってどんな成分?
みなさん、こんにちは。 今日の東京はとっても清々しい1日です。梅雨入りも近いみたいなので、こんな日は海にでも行ってパーーっと気晴らししていですね😊 さて、以前コエンザイムQ10が多く含まれる食品についてご紹介しました。おかげさまで反響もあり、 「コエンザイムQ10についてもっと詳しく知りたい!」 「コエンザイムサプリを飲もうか迷っている」 「コエンザイムq10のサプリを飲む必要があるの?」 など、コエンザイムQ10についてのご質問を数多く頂戴しておりますので、今回から少しの間コエンザイムQ10についてお話できればと思います。 コエンザイムQ10は、簡単に言うと、皆さんが元気に生きていく為に決して欠かすことのできない成分と言えます。また、このコエンザイムQ10は、皆さんの体内でも生成されています。 私たちの体内には、おおよそ37兆個もの細胞が存在しています。そして、そこには生命活動に欠かすことのできないエネルギーを作り出す工場である”ミトコンドリア”と呼ばれるものが存在します。 そして、”ミトコンドリア”において、生命活動、かつ、元気に生きていく為に必要となる[エネルギー]を作り出すためには、酸素の他に、食事から摂り入れた栄養、そして、体内にあるコエンザイムQ10が必要となります。 酸素は皆さん気にすることなく体内に取り入れていますが、体内生成や食事などでコエンザイムQ10をしっかり作り出し、また、摂り入れないと、エネルギーをうまく作り出すことができず、元気が出ない、疲れが取れないなどの症状が現れてしまいます。 次に、女性は特に気になる、抗酸化作用(身体のサビつき防止)です。先程、エネルギーを作り出すために酸素が必要であるとお伝えしました。また、酸素は生きていくために必要で、普段、当たり前のように体内にドンドン取り込んでいるものです。 そして、その体内に取り込んだ酸素の数%が、活性酸素と呼ばれる、いわゆる身体のサビの原因に変化してしまうことはご存知でしたでしょうか。 また、活性酸素は、年齢やストレス、食生活、太陽から浴びる紫外線、運動などによって、私たちの身体の中にドンドン生成されてしまい、体内にある37兆個もの細胞をドンドン傷つけてしまい、身体を酸化させてしまうのです。 ご存知の方も多いと思いますが、この活性酸素による身体の酸化(サビ)は、いわゆる老化を促進させてしまい、年齢よりも老けて見られたり、また、お肌のケアをしているにも関わらず、シミやしわ、お肌のたるみなどのお肌トラブルを引き起こしたり、生活習慣病をはじめとする体調不良なども引き起こしてしまうのです。 そこで、その身体の酸化を防いでくれる(=抗酸化作用)のも、実はコエンザイムQ10なのです。 他にも、コエンザイムQ10を摂取することで多くのメリットがありますが、それについては、また別の回でお話させていただくとして…次にとても重要なポイントをお伝えします。 コエンザイムQ10は、体内で生成されるから、問題ない!とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。しかし、いつまでも身体に必要なコエンザイムの量を生成できるわけではないんです。 コエンザイムQ10の体内での生成は、20歳をピークに減少しはじめ、40歳前後から、激減してしまうのです。 「さぁ、これからバリバリ行くぞー!」とか、「これからがお肌が気になる年齢!」という時に、一気に生成が減ってしまうのです。 では、どうすればよいか、というと、食事など外部からの摂取に頼るしかありません。 以前、コエンザイムQ10を含む食品についてブログを書きましたが、実は食品から摂取できるコエンザイムの量はとっても少ないのです。 一般的に1日に必要とされるコエンザイムの摂取目安量は100mgと言われていますが、それらをすべて食品から摂取しようとすると大変な食事量になってしまうのです。 例えば、ステーキだと20枚、いわしだと20匹、ブロッコリーだと12キロ… とっても大変ですよね💦 「そんなに摂れないからコエンザイムQ10は摂れるだけとりあえず摂っておけばいいか」、と考えられる方も多いですよね。 そこで、次回は、「なるほど!それはコエンザイムQ10を頑張って摂ろう!」と思えるようなメリットをいくつかご紹介できればと思っていますので、是非、次回のブログでチェックしてみてくださいね。 ということで、長くなってしまいましたので、ここまで。...
コエンザイムQ10ってどんな成分?
みなさん、こんにちは。 今日の東京はとっても清々しい1日です。梅雨入りも近いみたいなので、こんな日は海にでも行ってパーーっと気晴らししていですね😊 さて、以前コエンザイムQ10が多く含まれる食品についてご紹介しました。おかげさまで反響もあり、 「コエンザイムQ10についてもっと詳しく知りたい!」 「コエンザイムサプリを飲もうか迷っている」 「コエンザイムq10のサプリを飲む必要があるの?」 など、コエンザイムQ10についてのご質問を数多く頂戴しておりますので、今回から少しの間コエンザイムQ10についてお話できればと思います。 コエンザイムQ10は、簡単に言うと、皆さんが元気に生きていく為に決して欠かすことのできない成分と言えます。また、このコエンザイムQ10は、皆さんの体内でも生成されています。 私たちの体内には、おおよそ37兆個もの細胞が存在しています。そして、そこには生命活動に欠かすことのできないエネルギーを作り出す工場である”ミトコンドリア”と呼ばれるものが存在します。 そして、”ミトコンドリア”において、生命活動、かつ、元気に生きていく為に必要となる[エネルギー]を作り出すためには、酸素の他に、食事から摂り入れた栄養、そして、体内にあるコエンザイムQ10が必要となります。 酸素は皆さん気にすることなく体内に取り入れていますが、体内生成や食事などでコエンザイムQ10をしっかり作り出し、また、摂り入れないと、エネルギーをうまく作り出すことができず、元気が出ない、疲れが取れないなどの症状が現れてしまいます。 次に、女性は特に気になる、抗酸化作用(身体のサビつき防止)です。先程、エネルギーを作り出すために酸素が必要であるとお伝えしました。また、酸素は生きていくために必要で、普段、当たり前のように体内にドンドン取り込んでいるものです。 そして、その体内に取り込んだ酸素の数%が、活性酸素と呼ばれる、いわゆる身体のサビの原因に変化してしまうことはご存知でしたでしょうか。 また、活性酸素は、年齢やストレス、食生活、太陽から浴びる紫外線、運動などによって、私たちの身体の中にドンドン生成されてしまい、体内にある37兆個もの細胞をドンドン傷つけてしまい、身体を酸化させてしまうのです。 ご存知の方も多いと思いますが、この活性酸素による身体の酸化(サビ)は、いわゆる老化を促進させてしまい、年齢よりも老けて見られたり、また、お肌のケアをしているにも関わらず、シミやしわ、お肌のたるみなどのお肌トラブルを引き起こしたり、生活習慣病をはじめとする体調不良なども引き起こしてしまうのです。 そこで、その身体の酸化を防いでくれる(=抗酸化作用)のも、実はコエンザイムQ10なのです。 他にも、コエンザイムQ10を摂取することで多くのメリットがありますが、それについては、また別の回でお話させていただくとして…次にとても重要なポイントをお伝えします。 コエンザイムQ10は、体内で生成されるから、問題ない!とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。しかし、いつまでも身体に必要なコエンザイムの量を生成できるわけではないんです。 コエンザイムQ10の体内での生成は、20歳をピークに減少しはじめ、40歳前後から、激減してしまうのです。 「さぁ、これからバリバリ行くぞー!」とか、「これからがお肌が気になる年齢!」という時に、一気に生成が減ってしまうのです。 では、どうすればよいか、というと、食事など外部からの摂取に頼るしかありません。 以前、コエンザイムQ10を含む食品についてブログを書きましたが、実は食品から摂取できるコエンザイムの量はとっても少ないのです。 一般的に1日に必要とされるコエンザイムの摂取目安量は100mgと言われていますが、それらをすべて食品から摂取しようとすると大変な食事量になってしまうのです。 例えば、ステーキだと20枚、いわしだと20匹、ブロッコリーだと12キロ… とっても大変ですよね💦 「そんなに摂れないからコエンザイムQ10は摂れるだけとりあえず摂っておけばいいか」、と考えられる方も多いですよね。 そこで、次回は、「なるほど!それはコエンザイムQ10を頑張って摂ろう!」と思えるようなメリットをいくつかご紹介できればと思っていますので、是非、次回のブログでチェックしてみてくださいね。 ということで、長くなってしまいましたので、ここまで。...

ビタミンB群を含む食品は?
みなさん、こんにちは。 あっと言う間にゴールデンウィークも終わってしまいましたね💦次の大型連休は夏休みですかね!その日を楽しみに、また元気に過ごしていきましょう😊 さて、先日までは、ビタミンB群のそれぞれの栄養素についてお話させて頂きました。 ビタミンB群の役割(その1) ビタミンB群の役割(その2) それでは、本日はビタミンB群を含む食品を見ていきましょう。 ■ビタミンB1を含む食品、食材 豚ヒレ肉 豚モモ肉 うなぎ かつお まぐろの赤身 たらこ 黒豆 枝豆 豆腐(絹) 玄米 など ■ビタミンB2を含む食品、食材 豚レバー うなぎ ぶり さわら ほうれん草 納豆 牛乳 アーモンド など ■ビタミンB6を含む食品、食材 かつお...
ビタミンB群を含む食品は?
みなさん、こんにちは。 あっと言う間にゴールデンウィークも終わってしまいましたね💦次の大型連休は夏休みですかね!その日を楽しみに、また元気に過ごしていきましょう😊 さて、先日までは、ビタミンB群のそれぞれの栄養素についてお話させて頂きました。 ビタミンB群の役割(その1) ビタミンB群の役割(その2) それでは、本日はビタミンB群を含む食品を見ていきましょう。 ■ビタミンB1を含む食品、食材 豚ヒレ肉 豚モモ肉 うなぎ かつお まぐろの赤身 たらこ 黒豆 枝豆 豆腐(絹) 玄米 など ■ビタミンB2を含む食品、食材 豚レバー うなぎ ぶり さわら ほうれん草 納豆 牛乳 アーモンド など ■ビタミンB6を含む食品、食材 かつお...

ビタミンB群の役割(その2)
みなさん、こんにちは。 ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか😊明日からは天気も良くなるようですので、行楽日和ですね! さて、先日のブログでは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12についてお話させて頂きました。今回のブログでは、残りの4つのお話をさせていただきますね。 まずは、おさらい。 ■ビタミンB群とは? ビタミンB群とは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビオチン(ビタミンB7)、葉酸(ビタミンB9)の8種類からなる、ビタミン複合体のことを指します。これらのビタミンは、単体で摂ることよりも、同時に摂取することで、ビタミンB同士が助け合うことで効果が出るため、「ビタミンB群」と呼ばれている。 ビタミンB群は、水溶性のビタミンです。それは、食事などから摂取したビタミンB群は、尿によって排泄されてしまうため、身体に蓄えることができません。よって、一気にたくさんのビタミンB群を摂取するのではなく、日々継続的にビタミンB群を摂取していく必要がある。 ビタミンB群は、糖質(糖分)やたんぱく質などの栄養素を代謝する時に、酵素を助けて補酵素になる必須ビタミン。また、エネルギーがスムーズに作られることから、疲労回復はもちろん、ダイエットやお肌のハリやみずみずしさなどのコンディションを整えてくれる、美容面でも欠かせない栄養素と言える。 ・・・ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12についてはこちらから。 それでは、ビタミンB群のナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビオチン(ビタミンB7)、葉酸(ビタミンB9)についてお話していきましょう。 [ナイアシン(ビタミンB3)] ●ナイアシン(ビタミンB3)の役割とは? ナイアシン(ビタミンB3)は、脂質やタンパク質(アミノ酸)をエネルギーに変換する(代謝する)役割があります。また、他のビタミンBと同様に、皮膚や粘膜を健康に保つ役割も。 ●ナイアシン(ビタミンB3)はどうすると不足するの? ナイアシン(ビタミンB3)は、お酒を飲むと失われやすいので、 お酒を飲む頻度が多い方は積極的に摂取するのがよいでしょう。 ●ナイアシン(ビタミンB3)が不足すると? ナイアシン(ビタミンB3)が不足すると、イライラが増えてしまったり、精神的に不安定になると言われています。また、皮膚炎や口内炎、その他、消化不良や食欲不振などの症状も現れてきます。 [パントテン酸(ビタミンB5)] ●パントテン酸(ビタミンB5)の役割とは? パントテン酸(ビタミンB5)は、糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換する役割があります。パントテン酸(ビタミンB5)は、エネルギー代謝において働くコエンザイムAという補酵素の構成成分でもあります。なお、パントテン酸(ビタミンB5)においても、他のビタミンB同様に皮膚や粘膜の健康維持の役割も持っております。 ●パントテン酸(ビタミンB5)はどうすると不足するの? パントテン酸(ビタミンB5)については、様々な食品に含まれており、不足することがないと言われている栄養素です。 ●パントテン酸(ビタミンB5)が不足すると? パントテン酸(ビタミンB5)が不足すると、 頭痛や手足のしびれなどの症状が現れます。その他、疲労感や食欲不振などの症状も。 [ビオチン(ビタミンB7)] ●ビオチン(ビタミンB7)の役割とは? ビオチン(ビタミンB7)は、パントテン酸(ビタミンB5)と同様に、糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換する役割と、皮膚の健康を維持する役割も担っています。...
ビタミンB群の役割(その2)
みなさん、こんにちは。 ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか😊明日からは天気も良くなるようですので、行楽日和ですね! さて、先日のブログでは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12についてお話させて頂きました。今回のブログでは、残りの4つのお話をさせていただきますね。 まずは、おさらい。 ■ビタミンB群とは? ビタミンB群とは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビオチン(ビタミンB7)、葉酸(ビタミンB9)の8種類からなる、ビタミン複合体のことを指します。これらのビタミンは、単体で摂ることよりも、同時に摂取することで、ビタミンB同士が助け合うことで効果が出るため、「ビタミンB群」と呼ばれている。 ビタミンB群は、水溶性のビタミンです。それは、食事などから摂取したビタミンB群は、尿によって排泄されてしまうため、身体に蓄えることができません。よって、一気にたくさんのビタミンB群を摂取するのではなく、日々継続的にビタミンB群を摂取していく必要がある。 ビタミンB群は、糖質(糖分)やたんぱく質などの栄養素を代謝する時に、酵素を助けて補酵素になる必須ビタミン。また、エネルギーがスムーズに作られることから、疲労回復はもちろん、ダイエットやお肌のハリやみずみずしさなどのコンディションを整えてくれる、美容面でも欠かせない栄養素と言える。 ・・・ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12についてはこちらから。 それでは、ビタミンB群のナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビオチン(ビタミンB7)、葉酸(ビタミンB9)についてお話していきましょう。 [ナイアシン(ビタミンB3)] ●ナイアシン(ビタミンB3)の役割とは? ナイアシン(ビタミンB3)は、脂質やタンパク質(アミノ酸)をエネルギーに変換する(代謝する)役割があります。また、他のビタミンBと同様に、皮膚や粘膜を健康に保つ役割も。 ●ナイアシン(ビタミンB3)はどうすると不足するの? ナイアシン(ビタミンB3)は、お酒を飲むと失われやすいので、 お酒を飲む頻度が多い方は積極的に摂取するのがよいでしょう。 ●ナイアシン(ビタミンB3)が不足すると? ナイアシン(ビタミンB3)が不足すると、イライラが増えてしまったり、精神的に不安定になると言われています。また、皮膚炎や口内炎、その他、消化不良や食欲不振などの症状も現れてきます。 [パントテン酸(ビタミンB5)] ●パントテン酸(ビタミンB5)の役割とは? パントテン酸(ビタミンB5)は、糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換する役割があります。パントテン酸(ビタミンB5)は、エネルギー代謝において働くコエンザイムAという補酵素の構成成分でもあります。なお、パントテン酸(ビタミンB5)においても、他のビタミンB同様に皮膚や粘膜の健康維持の役割も持っております。 ●パントテン酸(ビタミンB5)はどうすると不足するの? パントテン酸(ビタミンB5)については、様々な食品に含まれており、不足することがないと言われている栄養素です。 ●パントテン酸(ビタミンB5)が不足すると? パントテン酸(ビタミンB5)が不足すると、 頭痛や手足のしびれなどの症状が現れます。その他、疲労感や食欲不振などの症状も。 [ビオチン(ビタミンB7)] ●ビオチン(ビタミンB7)の役割とは? ビオチン(ビタミンB7)は、パントテン酸(ビタミンB5)と同様に、糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変換する役割と、皮膚の健康を維持する役割も担っています。...

ビタミンB群の役割(その1)
みなさん、こんにちは。 いよいよ明日からゴールデンウィーク!ここ何年かはなかなか外出もできませんでしたが、今年は出掛けるぞ!という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。めいっぱい楽しんで来てくださいね😊 さて、今回は、ビタミンB群についてお話していきたいと思います。ビタミンってたくさんあるので、何が何だかよくわからない、というご質問を良く受けます。ナマサプリでも、ビタミンB群サプリ以外に、ビタミンC サプリ、ビタミンE サプリ、マルチビタミン サプリと様々なビタミンサプリを取り扱っており、それぞれに役割がありますので、その辺りも含めてお話できればと思います。 ■ビタミンB群とは? ビタミンB群とは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビオチン(ビタミンB7)、葉酸(ビタミンB9)の8種類からなる、ビタミン複合体のことを指します。これらのビタミンは、単体で摂ることよりも、同時に摂取することで、ビタミンB同士が助け合うことで効果が出るため、「ビタミンB群」と呼ばれています。 また、ビタミンB群は、水溶性のビタミンです。それは、食事などから摂取したビタミンB群は、尿によって排泄されてしまうため、身体に蓄えることができません。よって、一気にたくさんのビタミンB群を摂取するのではなく、日々継続的にビタミンB群を摂取していく必要があります。 ビタミンB群は、糖質(糖分)やたんぱく質などの栄養素を代謝する時に、酵素を助けて補酵素になる必須ビタミン。また、エネルギーがスムーズに作られることから、疲労回復はもちろん、ダイエットやお肌のハリやみずみずしさなどのコンディションを整えてくれる、美容面でも欠かせない栄養素と言えます。詳細は以下でご説明していきます。 [ビタミンB1] ●ビタミンB1の役割とは? ビタミンB1には、糖質をエネルギーに変換する役割があります。また、皮膚や粘膜の健康維持をサポートする役割、脳や神経の働きをサポートする役割などもあります。 ●ビタミンB1はどうすると不足するの? ご飯、ラーメン、パンなどの炭水化物の摂取(不規則な食生活)が多い方やお酒などのアルコールを飲む機会が多い方はビタミンB1が不足しやすくなります。 ●ビタミンB1が不足すると? 糖質の代謝がうまくできなくなるため、疲労感や、だるさ、肩こりや筋肉痛などの原因となってしまいます。また、集中力が低下したり、お酒を飲んだ次の日に辛い二日酔いなどの原因にもなりえます。 [ビタミンB2] ●ビタミンB2の役割とは? ビタミンB2には、脂質をエネルギーに変換する役割があります。また、皮膚や粘膜の健康維持をサポートする役割もあります。 ●ビタミンB2はどうすると不足するの? ビタミンB2は脂質代謝に関わる補酵素ですので、脂質を多く含む食事などを多くされる方は、ビタミンB2が不足する傾向にあると言えます。 ●ビタミンB2が不足すると? 脂質の代謝がうまくできなくなることで、口内炎や粘膜に炎症を起こしたりする場合があります。また、成長スピードが落ちるとも言われています。 [ビタミンB6] ●ビタミンB6の役割とは? ビタミンB6には、タンパク質からエネルギーを産み出す役割があります。また、アミノ酸の再合成(分解と吸収)をサポートする補酵素でもあるため、トレーニングやダイエットなどをしている方には、タンパク質と一緒に摂取すべき栄養素です。その他皮膚や粘膜の健康維持もサポートする役割があります。 ●ビタミンB6はどうすると不足するの? ビタミンB6は、タンパク質を摂取すればするほどビタミンB6が必要となるので、筋トレやダイエットなどで、プロテインを飲んでいる方は積極的に摂取すべき栄養素です。...
ビタミンB群の役割(その1)
みなさん、こんにちは。 いよいよ明日からゴールデンウィーク!ここ何年かはなかなか外出もできませんでしたが、今年は出掛けるぞ!という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。めいっぱい楽しんで来てくださいね😊 さて、今回は、ビタミンB群についてお話していきたいと思います。ビタミンってたくさんあるので、何が何だかよくわからない、というご質問を良く受けます。ナマサプリでも、ビタミンB群サプリ以外に、ビタミンC サプリ、ビタミンE サプリ、マルチビタミン サプリと様々なビタミンサプリを取り扱っており、それぞれに役割がありますので、その辺りも含めてお話できればと思います。 ■ビタミンB群とは? ビタミンB群とは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビオチン(ビタミンB7)、葉酸(ビタミンB9)の8種類からなる、ビタミン複合体のことを指します。これらのビタミンは、単体で摂ることよりも、同時に摂取することで、ビタミンB同士が助け合うことで効果が出るため、「ビタミンB群」と呼ばれています。 また、ビタミンB群は、水溶性のビタミンです。それは、食事などから摂取したビタミンB群は、尿によって排泄されてしまうため、身体に蓄えることができません。よって、一気にたくさんのビタミンB群を摂取するのではなく、日々継続的にビタミンB群を摂取していく必要があります。 ビタミンB群は、糖質(糖分)やたんぱく質などの栄養素を代謝する時に、酵素を助けて補酵素になる必須ビタミン。また、エネルギーがスムーズに作られることから、疲労回復はもちろん、ダイエットやお肌のハリやみずみずしさなどのコンディションを整えてくれる、美容面でも欠かせない栄養素と言えます。詳細は以下でご説明していきます。 [ビタミンB1] ●ビタミンB1の役割とは? ビタミンB1には、糖質をエネルギーに変換する役割があります。また、皮膚や粘膜の健康維持をサポートする役割、脳や神経の働きをサポートする役割などもあります。 ●ビタミンB1はどうすると不足するの? ご飯、ラーメン、パンなどの炭水化物の摂取(不規則な食生活)が多い方やお酒などのアルコールを飲む機会が多い方はビタミンB1が不足しやすくなります。 ●ビタミンB1が不足すると? 糖質の代謝がうまくできなくなるため、疲労感や、だるさ、肩こりや筋肉痛などの原因となってしまいます。また、集中力が低下したり、お酒を飲んだ次の日に辛い二日酔いなどの原因にもなりえます。 [ビタミンB2] ●ビタミンB2の役割とは? ビタミンB2には、脂質をエネルギーに変換する役割があります。また、皮膚や粘膜の健康維持をサポートする役割もあります。 ●ビタミンB2はどうすると不足するの? ビタミンB2は脂質代謝に関わる補酵素ですので、脂質を多く含む食事などを多くされる方は、ビタミンB2が不足する傾向にあると言えます。 ●ビタミンB2が不足すると? 脂質の代謝がうまくできなくなることで、口内炎や粘膜に炎症を起こしたりする場合があります。また、成長スピードが落ちるとも言われています。 [ビタミンB6] ●ビタミンB6の役割とは? ビタミンB6には、タンパク質からエネルギーを産み出す役割があります。また、アミノ酸の再合成(分解と吸収)をサポートする補酵素でもあるため、トレーニングやダイエットなどをしている方には、タンパク質と一緒に摂取すべき栄養素です。その他皮膚や粘膜の健康維持もサポートする役割があります。 ●ビタミンB6はどうすると不足するの? ビタミンB6は、タンパク質を摂取すればするほどビタミンB6が必要となるので、筋トレやダイエットなどで、プロテインを飲んでいる方は積極的に摂取すべき栄養素です。...
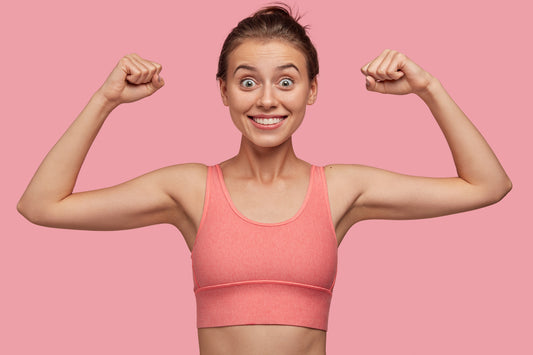
ヘム鉄と非ヘム鉄
みなさん、こんにちは😊 季節の変わり目は急に天気が変わって困りますね💦 外出の際は折りたたみ傘を忘れずに! さて、先日のブログでは、なぜ鉄分不足になるのか、また、鉄分不足のチェック項目をお話させて頂きました。 本日は、ヘム鉄と非ヘム鉄、また、どんな食品に含まれているか、についてお話させて頂ければと思います。 ■ヘム鉄と非ヘム鉄について 鉄には、ヘム鉄と非ヘム鉄の2種類が存在します。それぞれについては以下にご説明させて頂きます。 [ヘム鉄] 一般的に非ヘム鉄よりも吸収率が高いとされ、その鉄の体内への吸収率は10%〜20%と言われており、お肉やお魚などの動物性食品に多く含まれています。 [非ヘム鉄] 一方、非ヘム鉄はヘム鉄よりも吸収率は低く、鉄の体内への吸収率は2%〜5%程度と言われています。しかしながら、ビタミンCと一緒に摂取することで吸収率を上げることもできます。なお、非ヘム鉄は、お野菜や大豆類などの植物性食品に多く含まれています。 後述しますが、動物性食品だけで食事をし続けることは難しいため、ヘム鉄と非ヘム鉄、そして、ビタミンCを摂取することが、効率よく鉄分を体内に補給することができる、ということですね。 なお、タンニンは鉄の吸収を阻害すると言われています。よって、食事中は、お水や麦茶などにすることが望ましく、食後のコーヒーについては、(なかなか難しいですが…)食後3時間程度置いてからの方が、鉄の吸収には優しいかもしれません。 ■どんな食品に鉄は含まれている? ヘム鉄を含む代表的な動物性食品 煮干し 豚レバー しじみ 鶏レバー 牛ヒレ肉 牛レバー カツオ 真いわし 牡蠣 非ヘム鉄を含む代表的な植物性食品 厚揚げ 小松菜...
ヘム鉄と非ヘム鉄
みなさん、こんにちは😊 季節の変わり目は急に天気が変わって困りますね💦 外出の際は折りたたみ傘を忘れずに! さて、先日のブログでは、なぜ鉄分不足になるのか、また、鉄分不足のチェック項目をお話させて頂きました。 本日は、ヘム鉄と非ヘム鉄、また、どんな食品に含まれているか、についてお話させて頂ければと思います。 ■ヘム鉄と非ヘム鉄について 鉄には、ヘム鉄と非ヘム鉄の2種類が存在します。それぞれについては以下にご説明させて頂きます。 [ヘム鉄] 一般的に非ヘム鉄よりも吸収率が高いとされ、その鉄の体内への吸収率は10%〜20%と言われており、お肉やお魚などの動物性食品に多く含まれています。 [非ヘム鉄] 一方、非ヘム鉄はヘム鉄よりも吸収率は低く、鉄の体内への吸収率は2%〜5%程度と言われています。しかしながら、ビタミンCと一緒に摂取することで吸収率を上げることもできます。なお、非ヘム鉄は、お野菜や大豆類などの植物性食品に多く含まれています。 後述しますが、動物性食品だけで食事をし続けることは難しいため、ヘム鉄と非ヘム鉄、そして、ビタミンCを摂取することが、効率よく鉄分を体内に補給することができる、ということですね。 なお、タンニンは鉄の吸収を阻害すると言われています。よって、食事中は、お水や麦茶などにすることが望ましく、食後のコーヒーについては、(なかなか難しいですが…)食後3時間程度置いてからの方が、鉄の吸収には優しいかもしれません。 ■どんな食品に鉄は含まれている? ヘム鉄を含む代表的な動物性食品 煮干し 豚レバー しじみ 鶏レバー 牛ヒレ肉 牛レバー カツオ 真いわし 牡蠣 非ヘム鉄を含む代表的な植物性食品 厚揚げ 小松菜...
