ナマサプリBLOG
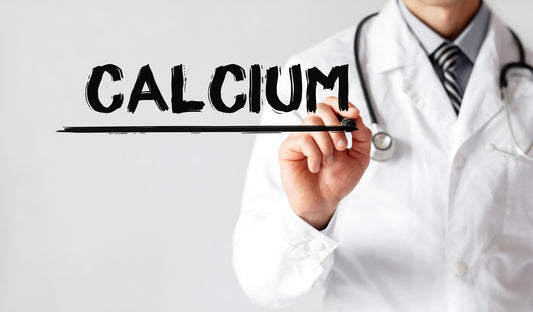
カルシウムは骨と歯だけじゃない!
みなさん、こんにちは。 今日から6月のはじまりですね。おおお、あっという間に今年もこの1ヶ月で半分を終えようとしているなんて😅1日1日を大切に過ごしたいですね! さて、本日はカルシウムについてシェアしたいと思います。カルシウムは骨や歯の形成に必要であることはご存知かと思いますが、実は、カルシウムの役割はそれだけではありません。生命維持に欠かせないカルシウムについてお話させていただきます。 [カルシウムとは?] カルシウムの役割をお伝えする前に、そもそも、カルシウムとはどんな栄養素なのかについてお話したいと思います。 カルシウムは、歯や骨を作り出す為に必要なミネラルのひとつです。そして、日本人に不足しやすいミネラルでもあります。カルシウムは、私たち人間のからだのなかに存在するミネラルで最も多く、体重のおよそ1〜2%を占めています。また、からだのなかにあるカルシウムのうち、およそ99%のカルシウムは、歯や骨などに存在し、残りのおよそ1%のカルシウムは、血液や筋肉、神経などに存在しています。 [カルシウムの役割] カルシウムがどれだけ私たちにとって大切なものかを以下に挙げさせていただきます。 骨や歯を形成する いらいらを鎮め、神経の興奮を抑える 血液凝固作用の促進 細胞の分裂、分化 抗アレルギー作用 など 骨は、およそ3ヶ月サイクルで、骨の形成と骨の吸収を繰り返しており、成長期には骨の吸収量よりも、骨の形成量の方が多く、骨量は増加しますが、男性は50代から、女性は閉経後にそれらが逆転してしまい、骨の吸収量が形成量を上回るため、しっかりとした骨を保つためには、歳を重ねる毎に、よりカルシウム摂取が重要になってきます。 [カルシウムが不足すると] 次に、カルシウムが不足してしますと、どんな症状が起きるかについて。 冒頭でも書きましたが、カルシウムは不足しがちなミネラルの一つです。そして、カルシウムが不足してしまうと、骨や歯が弱くり、骨折しやすくなってしまったり、肩こりや腰痛などを引き起こします。また、歳を重ねる毎に、カルシウム濃度は減少してしまい、特に閉経後の女性は骨粗しょう症を起こしやすくなると言われています。なお、幼児のカルシウム不足も深刻で、骨の発育に障害が起こることで、骨の発達障害にもつながるため、カルシウム摂取はとても重要であると言えます。 いかがでしたでしょうか。カルシウムが体内で不足してしまうと、いつまでも元気に生活していく上で、大きな支障をきたしてしまうため、他の栄養素と同様に、積極的に摂取することをオススメします! 次回では、カルシウムを含む食品、食材についてお伝えできればと思います😊 本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。 それでは、またお逢いしましょー! [栄養機能食品] カルシウム+マグネシウム+ビタミンD 62種類の植物発酵エキス+国産玄米末サプリ 安心・安全国産サプリメント通販 ナマサプリ 公式ストア
カルシウムは骨と歯だけじゃない!
みなさん、こんにちは。 今日から6月のはじまりですね。おおお、あっという間に今年もこの1ヶ月で半分を終えようとしているなんて😅1日1日を大切に過ごしたいですね! さて、本日はカルシウムについてシェアしたいと思います。カルシウムは骨や歯の形成に必要であることはご存知かと思いますが、実は、カルシウムの役割はそれだけではありません。生命維持に欠かせないカルシウムについてお話させていただきます。 [カルシウムとは?] カルシウムの役割をお伝えする前に、そもそも、カルシウムとはどんな栄養素なのかについてお話したいと思います。 カルシウムは、歯や骨を作り出す為に必要なミネラルのひとつです。そして、日本人に不足しやすいミネラルでもあります。カルシウムは、私たち人間のからだのなかに存在するミネラルで最も多く、体重のおよそ1〜2%を占めています。また、からだのなかにあるカルシウムのうち、およそ99%のカルシウムは、歯や骨などに存在し、残りのおよそ1%のカルシウムは、血液や筋肉、神経などに存在しています。 [カルシウムの役割] カルシウムがどれだけ私たちにとって大切なものかを以下に挙げさせていただきます。 骨や歯を形成する いらいらを鎮め、神経の興奮を抑える 血液凝固作用の促進 細胞の分裂、分化 抗アレルギー作用 など 骨は、およそ3ヶ月サイクルで、骨の形成と骨の吸収を繰り返しており、成長期には骨の吸収量よりも、骨の形成量の方が多く、骨量は増加しますが、男性は50代から、女性は閉経後にそれらが逆転してしまい、骨の吸収量が形成量を上回るため、しっかりとした骨を保つためには、歳を重ねる毎に、よりカルシウム摂取が重要になってきます。 [カルシウムが不足すると] 次に、カルシウムが不足してしますと、どんな症状が起きるかについて。 冒頭でも書きましたが、カルシウムは不足しがちなミネラルの一つです。そして、カルシウムが不足してしまうと、骨や歯が弱くり、骨折しやすくなってしまったり、肩こりや腰痛などを引き起こします。また、歳を重ねる毎に、カルシウム濃度は減少してしまい、特に閉経後の女性は骨粗しょう症を起こしやすくなると言われています。なお、幼児のカルシウム不足も深刻で、骨の発育に障害が起こることで、骨の発達障害にもつながるため、カルシウム摂取はとても重要であると言えます。 いかがでしたでしょうか。カルシウムが体内で不足してしまうと、いつまでも元気に生活していく上で、大きな支障をきたしてしまうため、他の栄養素と同様に、積極的に摂取することをオススメします! 次回では、カルシウムを含む食品、食材についてお伝えできればと思います😊 本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。 それでは、またお逢いしましょー! [栄養機能食品] カルシウム+マグネシウム+ビタミンD 62種類の植物発酵エキス+国産玄米末サプリ 安心・安全国産サプリメント通販 ナマサプリ 公式ストア

マルチビタミンってどんなもの?
みなさん、こんにちは。 週末はいかがでしたでしょうか。今週も始まりました!楽しい1週間にしたいですね😊 さて、先日、ビタミンCについてお話させて頂きましたが、私たちが健康に、そして元気に、美しく生活していくために、ビタミンがとっても大切な栄養素であることはお分かりいただけたかと思います😊 ところで、皆さんも耳にしたことがあると思いますが、ビタミンは、ビタミンCに限らず、ビタミンE、ビタミンB(群)など様々なビタミンがあります。 ナマサプリのお客様からも 「ビタミンの種類が多過ぎる💦」 「効率よくビタミンをまんべんなく摂りたい」 などのお話をいただきます。 そこで、今回からは、それら複数あるビタミンを効率よく摂取すべく、マルチビタミン(サプリ)についてお話させて頂きたいと思います。 [ビタミンの種類] ビタミンは、脂溶性ビタミンと、水溶性ビタミンの2つに分かれています。以前のブログでも書きましたが、ビタミンEは脂溶性ビタミンであり、ビタミンCは水溶性ビタミンでしたね。 脂溶性ビタミンには、ビタミンAやビタミンD、ビタミンEなどがあり、水溶性ビタミンには、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB3(ナイアシン)、ビタミンB5(パントテン酸)、葉酸などがあります。 以下では、それらの中からいくつかピックアップして主な特徴やそれらが含まれる食品、食材についてお話できればと思います。 [ビタミンA(βカロテン)] それでは、早速ですが、まずは、脂溶性ビタミンのビタミンAから。 ビタミンAは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称です。また、植物に含まれるβカロテンは、それを摂取すると、小腸上皮細胞でビタミンAにされるため、ビタミンAの前駆体「プロビタミンA」と言われ、ビタミンAに分類されています。 ビタミンAの特徴は、皮膚や粘膜を健やかに保ち、視覚に関わる色素タンパク質の生成などに関わっています。 ビタミンAを含む食品、食材としては、動物性食品ですと、豚・鶏レバーの他、うなぎに含まれ、また、βカロテンとして、にんじんやほうれん草などの緑黄色野菜にも多く含まれています。 お肌のカサつきや、暗いところで見えにくい方などはビタミAが足りていないかもしれませんので、摂取をオススメします。 [ビタミンD] 次に、脂溶性ビタミンであるビタミンDについて。 ビタミンDの特徴は、歯や骨の発育促進はもちろん、小腸においてカルシウムとリンの吸収を促進し、元気なカラダ作りに関わっています。 なお、ビタミンDについては、食品以外に、太陽(日光)に当たることでも生成することが可能です。なお、食品、食材からの摂取の場合は、鮭やさんま、しらすや干し椎茸などに多く含まれています。 ビタミンDは、魚類に多く含まれていますので、お魚をあまり食べない方や、あまり日光に当たらない方は、意識して摂取するといいでしょう。 [ビタミンE] ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持っているビタミンです。なお、ビタミンEは、油に溶けやすい性質を持った脂溶性のビタミンであり、実はビタミンEと呼ばれる成分にはいくつかの種類があり、それらをまとめて、ビタミンEと呼んでいます。 こちらについては、以前のブログに書かせて頂きましたので、是非以下からチェックしてみてください! ブログ:抗酸化成分、ビタミンEについて ブログ:ビタミンE不足に注意!...
マルチビタミンってどんなもの?
みなさん、こんにちは。 週末はいかがでしたでしょうか。今週も始まりました!楽しい1週間にしたいですね😊 さて、先日、ビタミンCについてお話させて頂きましたが、私たちが健康に、そして元気に、美しく生活していくために、ビタミンがとっても大切な栄養素であることはお分かりいただけたかと思います😊 ところで、皆さんも耳にしたことがあると思いますが、ビタミンは、ビタミンCに限らず、ビタミンE、ビタミンB(群)など様々なビタミンがあります。 ナマサプリのお客様からも 「ビタミンの種類が多過ぎる💦」 「効率よくビタミンをまんべんなく摂りたい」 などのお話をいただきます。 そこで、今回からは、それら複数あるビタミンを効率よく摂取すべく、マルチビタミン(サプリ)についてお話させて頂きたいと思います。 [ビタミンの種類] ビタミンは、脂溶性ビタミンと、水溶性ビタミンの2つに分かれています。以前のブログでも書きましたが、ビタミンEは脂溶性ビタミンであり、ビタミンCは水溶性ビタミンでしたね。 脂溶性ビタミンには、ビタミンAやビタミンD、ビタミンEなどがあり、水溶性ビタミンには、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB3(ナイアシン)、ビタミンB5(パントテン酸)、葉酸などがあります。 以下では、それらの中からいくつかピックアップして主な特徴やそれらが含まれる食品、食材についてお話できればと思います。 [ビタミンA(βカロテン)] それでは、早速ですが、まずは、脂溶性ビタミンのビタミンAから。 ビタミンAは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称です。また、植物に含まれるβカロテンは、それを摂取すると、小腸上皮細胞でビタミンAにされるため、ビタミンAの前駆体「プロビタミンA」と言われ、ビタミンAに分類されています。 ビタミンAの特徴は、皮膚や粘膜を健やかに保ち、視覚に関わる色素タンパク質の生成などに関わっています。 ビタミンAを含む食品、食材としては、動物性食品ですと、豚・鶏レバーの他、うなぎに含まれ、また、βカロテンとして、にんじんやほうれん草などの緑黄色野菜にも多く含まれています。 お肌のカサつきや、暗いところで見えにくい方などはビタミAが足りていないかもしれませんので、摂取をオススメします。 [ビタミンD] 次に、脂溶性ビタミンであるビタミンDについて。 ビタミンDの特徴は、歯や骨の発育促進はもちろん、小腸においてカルシウムとリンの吸収を促進し、元気なカラダ作りに関わっています。 なお、ビタミンDについては、食品以外に、太陽(日光)に当たることでも生成することが可能です。なお、食品、食材からの摂取の場合は、鮭やさんま、しらすや干し椎茸などに多く含まれています。 ビタミンDは、魚類に多く含まれていますので、お魚をあまり食べない方や、あまり日光に当たらない方は、意識して摂取するといいでしょう。 [ビタミンE] ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持っているビタミンです。なお、ビタミンEは、油に溶けやすい性質を持った脂溶性のビタミンであり、実はビタミンEと呼ばれる成分にはいくつかの種類があり、それらをまとめて、ビタミンEと呼んでいます。 こちらについては、以前のブログに書かせて頂きましたので、是非以下からチェックしてみてください! ブログ:抗酸化成分、ビタミンEについて ブログ:ビタミンE不足に注意!...

ビタミンCを摂るならこの食材を!
みなさん、こんにちは。 今日も清々しい東京です😊今週もあと少し!頑張っていきましょう〜。 さて、2回にわたってお話してきたビタミンC。今日は体内生成されないビタミンCをできるだけ効率よく摂取できるよう、ビタミンCを含む食材、食品をご紹介したいと思います。 [ビタミンCを含む食材、食品] ビタミンCは、以下の果物、野菜などに多く含まれています。 また、ビタミンCと一緒に鉄分やビタミンEを摂ることがオススメですので、以下のブログもチェックしてみてくださいね! ブログ:鉄分を含む食品 ブログ:ビタミンEを含む食品 食品・食材名 100g当たりのビタミンC含有量 アセロラ(生/酸味種) 1,700mg ケール 1,100mg アセロラ(生/甘味種) 800mg 煎茶 260mg 焼海苔 210mg 赤ピーマン(生) 170mg 黄ピーマン(生) 150mg ブロッコリー(生) 140mg すだち(生) 110mg 青ピーマン(生)...
ビタミンCを摂るならこの食材を!
みなさん、こんにちは。 今日も清々しい東京です😊今週もあと少し!頑張っていきましょう〜。 さて、2回にわたってお話してきたビタミンC。今日は体内生成されないビタミンCをできるだけ効率よく摂取できるよう、ビタミンCを含む食材、食品をご紹介したいと思います。 [ビタミンCを含む食材、食品] ビタミンCは、以下の果物、野菜などに多く含まれています。 また、ビタミンCと一緒に鉄分やビタミンEを摂ることがオススメですので、以下のブログもチェックしてみてくださいね! ブログ:鉄分を含む食品 ブログ:ビタミンEを含む食品 食品・食材名 100g当たりのビタミンC含有量 アセロラ(生/酸味種) 1,700mg ケール 1,100mg アセロラ(生/甘味種) 800mg 煎茶 260mg 焼海苔 210mg 赤ピーマン(生) 170mg 黄ピーマン(生) 150mg ブロッコリー(生) 140mg すだち(生) 110mg 青ピーマン(生)...

ビタミンC、不足してませんか?
みなさん、こんにちは。 今日の東京も暑いくらいの陽気です💦ただ、梅雨も間近なので、この太陽を大切にしたいですね😊 それでは、本日も前回に続き、ビタミンCについてお話させていただきます。 [ビタミンCが不足すると?] ビタミンCは、お肌だけでなく、多くのメリットがあることをお伝えさせて頂きました。では、そのビタミンCが不足すると私たちのからだにはどんなデメリットがあるのでしょうか。気になりますよね。以下にいくつか挙げさせていただきます。 肌荒れ 倦怠感 脱力感 疲労感 やる気、気力の低下 いらいら 血色悪化 食欲不振 歯肉炎 貧血 など ビタミンCが不足すると、コラーゲンが合成されないため、血管が弱くなるため、注意が必要です。また、ある研究では、ビタミンCが不足することで老化を促進させるとの結果も出ているんです。なお、ビタミンCは体内で生成することのできない栄養素ですので、積極的に食品やサプリから摂取する必要があります。 [ビタミンCが不足する原因は?] ここまでで、ビタミンCは、お肌に限らず、元気に、健康に生活していく上でもとても大切な栄養素であることがわかって頂けたかと思います。では、今度は、そのビタミンC、どうすると不足してしまうのか? 喫煙 過度、継続的なストレス 激しい運動 不規則な食生活 ダイエットによる偏食 重労働など などが挙げられます。 喫煙されている方はビタミンC不足が深刻ですので、積極的にビタミンCを摂取する、もしくは、できることならば…禁煙されることをオススメします💦また、現代では昔に比べ多くの方が何かしらのストレスを抱えていると思いますので、今を元気に生きていくためには、ビタミンCは必須栄養素であると言えますね。 いかがでしたでしょうか。 次回は、ビタミンCを効率的に摂取するために、ビタミンCを含む食品についてお話できればと思います😊 本日も最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。...
ビタミンC、不足してませんか?
みなさん、こんにちは。 今日の東京も暑いくらいの陽気です💦ただ、梅雨も間近なので、この太陽を大切にしたいですね😊 それでは、本日も前回に続き、ビタミンCについてお話させていただきます。 [ビタミンCが不足すると?] ビタミンCは、お肌だけでなく、多くのメリットがあることをお伝えさせて頂きました。では、そのビタミンCが不足すると私たちのからだにはどんなデメリットがあるのでしょうか。気になりますよね。以下にいくつか挙げさせていただきます。 肌荒れ 倦怠感 脱力感 疲労感 やる気、気力の低下 いらいら 血色悪化 食欲不振 歯肉炎 貧血 など ビタミンCが不足すると、コラーゲンが合成されないため、血管が弱くなるため、注意が必要です。また、ある研究では、ビタミンCが不足することで老化を促進させるとの結果も出ているんです。なお、ビタミンCは体内で生成することのできない栄養素ですので、積極的に食品やサプリから摂取する必要があります。 [ビタミンCが不足する原因は?] ここまでで、ビタミンCは、お肌に限らず、元気に、健康に生活していく上でもとても大切な栄養素であることがわかって頂けたかと思います。では、今度は、そのビタミンC、どうすると不足してしまうのか? 喫煙 過度、継続的なストレス 激しい運動 不規則な食生活 ダイエットによる偏食 重労働など などが挙げられます。 喫煙されている方はビタミンC不足が深刻ですので、積極的にビタミンCを摂取する、もしくは、できることならば…禁煙されることをオススメします💦また、現代では昔に比べ多くの方が何かしらのストレスを抱えていると思いますので、今を元気に生きていくためには、ビタミンCは必須栄養素であると言えますね。 いかがでしたでしょうか。 次回は、ビタミンCを効率的に摂取するために、ビタミンCを含む食品についてお話できればと思います😊 本日も最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。...

ビタミンCは美容だけじゃない!
みなさん、こんにちは。 そろそろ5月も終わりですね💦あっという間過ぎて怖すぎます… さて、今日からは数回に分けて、ビタミンCについてお話しようと思います。ビタミンCは皆さんもよく耳にする成分だと思いますが、ここで改めて大切さについて知って頂けたら嬉しいです😊 それでははじめていきましょう。 [ビタミンCとは] ビタミンCと聞くと、お肌の健康に不可欠、というイメージをお持ちの方も多いかと思います。もちろん、お肌に必要な成分ですが、それ以外にもとても大切な役割を持っています。ビタミンCがお肌に良いとイメージされるのは、コラーゲンの合成に不可欠な成分であるからかと思います。しかし、コラーゲンは、お肌だけでなく、からだの骨や血管などあらゆる細胞と細胞をつなげる要素もあるのです。また、ビタミンCは、それ自体のパワーはもちろんですが、鉄の吸収率をサポートする役割も担っています。以前のブログで、非ヘム鉄は含有量では勝るものの、ヘム鉄よりも吸収率が劣ってしまうというお話をしましたが、それをビタミンCが助けてくれるんです。 ブログ:ヘム鉄と非ヘム鉄 [ビタミンC摂取のメリット] それでは、実際にビタミンCを摂取することのメリットをいくつか挙げていきますね。 ■コラーゲン生成 私たちのからだの約30%を占めているコラーゲン。先程もお伝えしたように、コラーゲンは、肌だけでなく、血管や軟骨などに存在しており、細胞と細胞を繋げる役割を持っています。このコラーゲンを作り出すために、ビタミンCが書かせません。コラーゲンが足りなくなると、お肌への悪影響はもちろんですが、関節が痛くなったり、目が疲れたりなどの症状を引き起こします。 ■抗酸化作用 今までのブログで何度もお話させて頂いてきた、抗酸化作用ですが、ビタミンCにもその働きがあります。活性酸素が過剰に発生すると、お肌のしみやしわの原因になったり、また、生活習慣病、血管の病気などからだに悪影響をお呼びしますので、抗酸化作用のあるビタミンCはとても大切な成分と言えますね。 ■メラニン発生の抑制 しみやそばかす、日焼けなどの原因であるメラニン色素を抑えてくれる役割も持っているのがビタミンCです。 ■免疫力アップ ビタミンCを摂取することで、風邪などに掛かりやすくなったり、また、ガン予防になるとも言われています。 ビタミンC摂取のメリットをいくつか挙げさせて頂きましたが、いかがでしょうか。ビタミンCがお肌以外にも、私たちが健康に生きていく上で、とても大切な栄養素であることがお分かり頂けたと思います。 次回以降でもビタミンCについて様々なお話をさせて頂く予定ですので、是非ご覧になってくださいね! ということで、本日はここまで。 毎日を笑顔で、元気に、健康に過ごせすために、これからも美容、健康情報をお送りできればと思います。 最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました😊 1日にビタミンC1,050mg配合 [栄養機能食品]ビタミンCサプリメント 安心・安全国産サプリメント通販 ナマサプリ 公式ストア
ビタミンCは美容だけじゃない!
みなさん、こんにちは。 そろそろ5月も終わりですね💦あっという間過ぎて怖すぎます… さて、今日からは数回に分けて、ビタミンCについてお話しようと思います。ビタミンCは皆さんもよく耳にする成分だと思いますが、ここで改めて大切さについて知って頂けたら嬉しいです😊 それでははじめていきましょう。 [ビタミンCとは] ビタミンCと聞くと、お肌の健康に不可欠、というイメージをお持ちの方も多いかと思います。もちろん、お肌に必要な成分ですが、それ以外にもとても大切な役割を持っています。ビタミンCがお肌に良いとイメージされるのは、コラーゲンの合成に不可欠な成分であるからかと思います。しかし、コラーゲンは、お肌だけでなく、からだの骨や血管などあらゆる細胞と細胞をつなげる要素もあるのです。また、ビタミンCは、それ自体のパワーはもちろんですが、鉄の吸収率をサポートする役割も担っています。以前のブログで、非ヘム鉄は含有量では勝るものの、ヘム鉄よりも吸収率が劣ってしまうというお話をしましたが、それをビタミンCが助けてくれるんです。 ブログ:ヘム鉄と非ヘム鉄 [ビタミンC摂取のメリット] それでは、実際にビタミンCを摂取することのメリットをいくつか挙げていきますね。 ■コラーゲン生成 私たちのからだの約30%を占めているコラーゲン。先程もお伝えしたように、コラーゲンは、肌だけでなく、血管や軟骨などに存在しており、細胞と細胞を繋げる役割を持っています。このコラーゲンを作り出すために、ビタミンCが書かせません。コラーゲンが足りなくなると、お肌への悪影響はもちろんですが、関節が痛くなったり、目が疲れたりなどの症状を引き起こします。 ■抗酸化作用 今までのブログで何度もお話させて頂いてきた、抗酸化作用ですが、ビタミンCにもその働きがあります。活性酸素が過剰に発生すると、お肌のしみやしわの原因になったり、また、生活習慣病、血管の病気などからだに悪影響をお呼びしますので、抗酸化作用のあるビタミンCはとても大切な成分と言えますね。 ■メラニン発生の抑制 しみやそばかす、日焼けなどの原因であるメラニン色素を抑えてくれる役割も持っているのがビタミンCです。 ■免疫力アップ ビタミンCを摂取することで、風邪などに掛かりやすくなったり、また、ガン予防になるとも言われています。 ビタミンC摂取のメリットをいくつか挙げさせて頂きましたが、いかがでしょうか。ビタミンCがお肌以外にも、私たちが健康に生きていく上で、とても大切な栄養素であることがお分かり頂けたと思います。 次回以降でもビタミンCについて様々なお話をさせて頂く予定ですので、是非ご覧になってくださいね! ということで、本日はここまで。 毎日を笑顔で、元気に、健康に過ごせすために、これからも美容、健康情報をお送りできればと思います。 最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました😊 1日にビタミンC1,050mg配合 [栄養機能食品]ビタミンCサプリメント 安心・安全国産サプリメント通販 ナマサプリ 公式ストア

副腎ケア
みなさん、こんにちは。今週もはじまりましたね!元気よくいきましょう!😊 ということで、本日も、先週に続き、副腎のお話です。 【ベストセラー】「副腎の疲れ」をとれば老化もボケもくい止められる!」を世界一わかりやすく要約してみた【本要約】 引用:https://www.youtube.com/watch?v=3fzYUdLJRck 先日のブログでは、副腎について掲載させて頂いておりますので、気になる方はまずはそちらをチェックしてみてくださいね。 前回のブログ:副腎のお話。 それでは、早速ですが、副腎ケアについて紹介していきましょう。 [3つの副腎ケア] まず、副腎に大きな影響を与えているのは、食生活や食べ物。よって、ドカ食い、栄養不足、加工食品の摂り過ぎはもちろんNGです!悪い物を身体に入れないという事が大原則であることを忘れずに!そして「副腎ケア」をする為には「腸」の状態を整え、次に「肝臓」の負担の軽減させることが重要とのこと。そこで筆者が推奨しているうちの以下の3つを取り上げてみます。 グルテン、カゼイン、シュガーフリーを実践する 腸と副腎を元気にする栄養素を注入する 肝臓の負担を徹底的に減らす まずは、1の”3つのフリー”です。 「グルテン」とは小麦やライ麦などに含まれているタンパク質でモチモチしているもの。これがNGなんだそう。グルテンはパンの他に、ピザやパスタ、うどん等にも含まれていますが、このグルテンがアレルギー症状や炎症の原因になると言われていますのでグルテンを減らすことで腸内環境が改善され副腎の負担を軽減できます。 今では「グルテンフリー」という言葉はよく耳にするようになりましたよね。なんだかいつも調子が悪い、胃腸の状態が良くない、という方はグルテンの摂りすぎが原因かもしれません。 続いて「カゼイン」。「カゼイン」とは乳製品に含まれているタンパク質です。牛乳はもちろん、ヨーグルトやチーズなどにも含まれています。その「カゼイン」もアレルギー症状をひきおこし、アトピー性皮膚炎やめまい、花粉症などの症状を引き起こす可能性があるとのこと。 最後の「シュガー」フリーについては、私にとっても永遠の戦い…。腸のお掃除に加えて副腎の負担を減らすために控えるべきものの代表とも言えるお砂糖…疲れた時に甘いものを食べる習慣がある人が多いと思いますがそれは血糖値の乱高下を引き起こし、副腎に負担をかけます。砂糖は副腎だけでなく様々な病気にも関与しているので健康になりたいと思ったら真っ先に排除すべきもの…ですよね💦 食事は和食に、パンは玄米に、乳製品を豆乳製品に、乳酸菌を味噌やつけものから、カルシウムは小魚から、というように「副腎ケア」では食生活を改善する必要があるとのこと。また、甘いものには中毒症状がありますので、今まで食べてきたものをやめるのは最初は辛いと思いますが、長くても1ヶ月もすれば体調に変化が見られます。腸の吸収力が向上して身体の調子が良くなりますし、胃腸が強くなり、頭の中がすっきりします。是非チャレンジしてみましょう😊 続いては、2の”腸と副腎を元気にする栄養素を注入する”について。 何を注入すればよいか? それは、まずは、フィッシュオイル、です。サバやサンマ、サケ、イワシ、等に含まれるDHAやEPAはオメガ3系の不飽和脂肪酸がたくさん含まれていてそれらは身体の炎症を軽減してくれる効果があります。 次に注入すべきは、亜鉛、です。亜鉛は、炎症の修復にはかかせないものです。魚、アサリ、ハマグリ牡蠣等の亜鉛が多く含まれているものを積極的にとりましょう。 そして、最後が、ビタミンB群、です。副腎が疲れている人はビタミンB群が不足してる可能性があります。なぜかというと、「コルチゾール」のホルモンを作る為にはビタミンB群が大量に必要だからです!ビタミンB群は体内に蓄積できないので食べ物から常に摂る必要があります。 これらが食事で摂りきれないとお考えの方は悩まずにサプリメントに頼りましょう!なお、以前のブログで、亜鉛やビタミンB群についてお話しておりますので、是非あわせて読んでみてくださいね! ブログ:ビタミンB群の役割(その1)/ビタミンB群の役割(その2)/ビタミンB群を含む食品は? ブログ:亜鉛ってどんな成分なの?/亜鉛不足を防ぐおすすめ食材 最後に、3の”肝臓の負担を徹底的に減らす”について。 副腎疲労を軽減するために次に注目すべきなのは「解毒機能」がある肝臓。肝臓はアルコールをはじめとして食品添加物、整髪料や、化粧品、殺虫剤等の化学物質を解毒してくれる働きがあります。しかしながら、現代では様々な毒があり肝臓の解毒が追いついていないケースが多々あり、そうなると、身体に毒素が蓄積し、蓄積した毒素が身体のあちこちにまき散らされて炎症を起こします。炎症が起こるとその炎症を鎮めるためにコルチゾールが出動します。 つまり、肝臓への負担が大きくなると副腎にもそれが影響するというわけです。 肝臓の負担を減らすにはシンプルに不要な毒素を入れない、それにつきます。食品添加物の入った商品を出来るだけ食べない、アルコールも摂りすぎないように意識して飲むべきで、日用品のシャンプーや整髪料、歯磨き粉等も化学物質であるから出来るだけ体の中に入れない工夫が必要です。...
副腎ケア
みなさん、こんにちは。今週もはじまりましたね!元気よくいきましょう!😊 ということで、本日も、先週に続き、副腎のお話です。 【ベストセラー】「副腎の疲れ」をとれば老化もボケもくい止められる!」を世界一わかりやすく要約してみた【本要約】 引用:https://www.youtube.com/watch?v=3fzYUdLJRck 先日のブログでは、副腎について掲載させて頂いておりますので、気になる方はまずはそちらをチェックしてみてくださいね。 前回のブログ:副腎のお話。 それでは、早速ですが、副腎ケアについて紹介していきましょう。 [3つの副腎ケア] まず、副腎に大きな影響を与えているのは、食生活や食べ物。よって、ドカ食い、栄養不足、加工食品の摂り過ぎはもちろんNGです!悪い物を身体に入れないという事が大原則であることを忘れずに!そして「副腎ケア」をする為には「腸」の状態を整え、次に「肝臓」の負担の軽減させることが重要とのこと。そこで筆者が推奨しているうちの以下の3つを取り上げてみます。 グルテン、カゼイン、シュガーフリーを実践する 腸と副腎を元気にする栄養素を注入する 肝臓の負担を徹底的に減らす まずは、1の”3つのフリー”です。 「グルテン」とは小麦やライ麦などに含まれているタンパク質でモチモチしているもの。これがNGなんだそう。グルテンはパンの他に、ピザやパスタ、うどん等にも含まれていますが、このグルテンがアレルギー症状や炎症の原因になると言われていますのでグルテンを減らすことで腸内環境が改善され副腎の負担を軽減できます。 今では「グルテンフリー」という言葉はよく耳にするようになりましたよね。なんだかいつも調子が悪い、胃腸の状態が良くない、という方はグルテンの摂りすぎが原因かもしれません。 続いて「カゼイン」。「カゼイン」とは乳製品に含まれているタンパク質です。牛乳はもちろん、ヨーグルトやチーズなどにも含まれています。その「カゼイン」もアレルギー症状をひきおこし、アトピー性皮膚炎やめまい、花粉症などの症状を引き起こす可能性があるとのこと。 最後の「シュガー」フリーについては、私にとっても永遠の戦い…。腸のお掃除に加えて副腎の負担を減らすために控えるべきものの代表とも言えるお砂糖…疲れた時に甘いものを食べる習慣がある人が多いと思いますがそれは血糖値の乱高下を引き起こし、副腎に負担をかけます。砂糖は副腎だけでなく様々な病気にも関与しているので健康になりたいと思ったら真っ先に排除すべきもの…ですよね💦 食事は和食に、パンは玄米に、乳製品を豆乳製品に、乳酸菌を味噌やつけものから、カルシウムは小魚から、というように「副腎ケア」では食生活を改善する必要があるとのこと。また、甘いものには中毒症状がありますので、今まで食べてきたものをやめるのは最初は辛いと思いますが、長くても1ヶ月もすれば体調に変化が見られます。腸の吸収力が向上して身体の調子が良くなりますし、胃腸が強くなり、頭の中がすっきりします。是非チャレンジしてみましょう😊 続いては、2の”腸と副腎を元気にする栄養素を注入する”について。 何を注入すればよいか? それは、まずは、フィッシュオイル、です。サバやサンマ、サケ、イワシ、等に含まれるDHAやEPAはオメガ3系の不飽和脂肪酸がたくさん含まれていてそれらは身体の炎症を軽減してくれる効果があります。 次に注入すべきは、亜鉛、です。亜鉛は、炎症の修復にはかかせないものです。魚、アサリ、ハマグリ牡蠣等の亜鉛が多く含まれているものを積極的にとりましょう。 そして、最後が、ビタミンB群、です。副腎が疲れている人はビタミンB群が不足してる可能性があります。なぜかというと、「コルチゾール」のホルモンを作る為にはビタミンB群が大量に必要だからです!ビタミンB群は体内に蓄積できないので食べ物から常に摂る必要があります。 これらが食事で摂りきれないとお考えの方は悩まずにサプリメントに頼りましょう!なお、以前のブログで、亜鉛やビタミンB群についてお話しておりますので、是非あわせて読んでみてくださいね! ブログ:ビタミンB群の役割(その1)/ビタミンB群の役割(その2)/ビタミンB群を含む食品は? ブログ:亜鉛ってどんな成分なの?/亜鉛不足を防ぐおすすめ食材 最後に、3の”肝臓の負担を徹底的に減らす”について。 副腎疲労を軽減するために次に注目すべきなのは「解毒機能」がある肝臓。肝臓はアルコールをはじめとして食品添加物、整髪料や、化粧品、殺虫剤等の化学物質を解毒してくれる働きがあります。しかしながら、現代では様々な毒があり肝臓の解毒が追いついていないケースが多々あり、そうなると、身体に毒素が蓄積し、蓄積した毒素が身体のあちこちにまき散らされて炎症を起こします。炎症が起こるとその炎症を鎮めるためにコルチゾールが出動します。 つまり、肝臓への負担が大きくなると副腎にもそれが影響するというわけです。 肝臓の負担を減らすにはシンプルに不要な毒素を入れない、それにつきます。食品添加物の入った商品を出来るだけ食べない、アルコールも摂りすぎないように意識して飲むべきで、日用品のシャンプーや整髪料、歯磨き粉等も化学物質であるから出来るだけ体の中に入れない工夫が必要です。...
